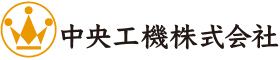中央工機の特別支援学校生徒さんの実習受け入れと雇用
2025年6月26日(水)に岐阜県立中濃特別支援学校にて開催された、「中濃特別支援学校雇用促進研修会」にてお話した内容をもとに構成しています。
当社が、特別支援学校の生徒さんの職場実習を受け入れたのは2019年。
2021年にその方を雇用し、まだ5年目です。
以前から障がいのある方も一緒に仕事をしていましたが、特別支援学校の生徒さんを職場実習に受入れ、その後の雇用はまったく初めてのことでした。
「さぁ、どうしよう?」からのスタートでしたが、「案ずるより産むがやすし」思うよりスムーズに進み、現在は(2025年6月時点)特別支援学校の卒業生4人と一緒に仕事をしています。
そんな経緯、わが社のリアルを紹介します。
初めての職場実習の受け入れ
中濃特別支援学校より、「当校の生徒の職業体験にご協力いただけませんか?」とお電話をいただいたのがきっかけでした。
このときは、就業につながるとは思ってもいませんでしたが、社会貢献の一貫として協力をすることにしました。
■ 職場実習を受け入れる前の考え
当社は、金属加工の限界に挑む難しい加工をしています。
多品種多工程少量という難しい受注に対応しているため、1日を通して同じ仕事をすることはなく、多種多様な仕事をしなくてはなりません。
そういった当社の特性からも、特別支援学校のみなさんには、うちの工場の仕事は難しいのではないか、と認識していました。
しかし、この認識は、のちに恥ずかしいほど未熟であったと気付かされます。
■ 中濃特別支援学校の生徒さんとの巡り合い
現在、当社で活躍しているKSさん。最初は親子で来社されました。
なぜ中央工機を職場体験先に選んでくださったのかと尋ねたところ、
親御さんがご友人に「どこかよい会社はないだろうか」と相談したら、「うちの会社ならきっといいよ」といわれたそう。
なんと当社の工場で働いている従業員が、特別支援学級の生徒さんの職場体験にふさわしい会社だと推薦してくれたことがわかりました。
会社のことをよく知っている従業員が推薦したのだから、うちには受け入れる要素があるにちがいない。
その期待に応え、KSさんにとってよい体験になるようにしようと、受け入れをすすめました。
職場体験 試行と工夫の実際(KSさんの事例)
まずは仕事をする意味を感じてもらう、働く体験をしてもらうよう計画
1回目(3日間):
- 工場を詳しく案内(→仕事の意味を感じる)
- 0.5日ずつの職場体験(→工場で働く体験をする)
<2回目以降も希望された>
2回目(5日間):1日ずつすべての職場(仕事)* を体験
3回目(5日間):本人が希望する職場2か所を体験
4回目(10日間):本人が希望する職場を10日間体験
*職場(仕事)= プレス加工 溶接加工 組立加工 出荷準備 管理
KSさんは、最終的に溶接職場を選択した。
■ KSさんを受け入れてわかったこと
やり方をわかりやすく伝えて作業の指導をすれば、どんなことでも正しくできる。
当社の仕事の多くができる。できることを増やしていける。
しかも、元気で朗らかでとにかく明るい。大きな声であいさつをする。
「あの子、いいね!」と、みんなに気に入られ人気者になった!
その後の展開 就業
KSさんは、職場体験を積み重ねることで、働くことの意味、意義、価値を感じることができた。
中央工機の中身を理解し、ここで働く自信を持った。
職場の人たちと良好な関係を作ることができ、安心してここで一緒に仕事ができると確信した。
会社としても、職場体験での仕事ぶり、人としての魅力、期待と可能性を高く評価し採用した。
● 2021年4月 入社 溶接チームに配属
■ KSさんのいま
KSさんは、この4年間スキルを順調に伸ばし、スポット溶接加工において難度がもっとも高い作業を担当しています。
円筒の中に部品を溶接するガス給湯器の排気部にかかわる作業は、気密性が要求される上に寸法精度が厳しい。
さらに外観品質も重要な加工で、誰にでもできる仕事ではない!


スキルの伸びだけではなく、
・職場の安全衛生委員を担当(2023年)
・親睦会「とうめい会」の役員(2024年)
・職場忘年会幹事(2024年)
・中濃特別支援学校での講話講師(2023年)
・中濃特別支援学校教職員様工場見学会のアテンド(2024年)
さまざまな場面で活躍し、同僚からの信頼度が高い。
社会人として成長した!
KSさんに引き続き、中濃特別支援学校、清流高等特別支援学校からの「職場体験」、「職場実習」を継続的に受け入れて、その方々を採用し、いま4人が活躍しています。
*引き続き2026年就業を計画し「職場体験」を受け入れています。
当社の「職場体験」のプログラム
1年生(職場体験・仕事って何?)
詳細な工場見学をしながら仕事の意義、価値を感じてもらう
2年生(やってみたいことを探す)
当社の仕事の全部を体験してもらう
3年生(実際にその仕事に従事する 仕事に楽しみを見出す)
1回目:希望する職場を2つ選び体験してもらう
2回目:上記2つから1つを選び体験してもらう
職場のメンバーと信頼関係を築く
■ 「職場体験」の流れ
- [1]学校からの打診
希望者の概略の情報 日程などを協議
<受入れOKの場合>
- [2]本人と親御さんがご一緒に来社 → 親御さんに安心してもらう。信頼関係が築ける
工場をご案内して面談 詳細の打ち合わせ
- [0](初回のみ)学校の進路指導の先生がご来社 → 本人の得意不得意が事前にわかる
ご本人の詳細な情報のご提供
[1],[2]は毎回あり
職場体験をした人を必ず雇用しなければならないわけではない
相互に合う合わないを判断する機会です

■ 「職場体験メリット」
- 4回の「職場体験」をすると、計20日程度の仕事を体験をすることができる。実作業として仕事の内容を理解できる。
- 体験の様子をみることで、何ができて、何が不得意なのかを知ることができる。
- 一緒に仕事をすることで相互の信頼関係が築ける。
- 親御さんと会話することで、ご家族のご理解が深まり安心される。
- 本人が仕事の流れ、職場の雰囲気に慣れることで安心して働く自信を得る。働く準備ができる。
- 仕事の楽しみを感じてもらえる。
- あるいは、当社の仕事が合わないことも分かる。

まずは「職場体験」を受け入れてください
企業運営にはいろんな考えがあってよいと思います。
しかし扉を閉じたままでは考えは変わりません。また受入れは従業員にとっても障がいのある方について学び理解を深めるチャンスになります。
課題
■ 障がい者雇用にかかる課題のひとつ「通勤距離」
通勤距離は本人、ご家族にとって大きな課題です。
会社側にとっても安全に通勤してもらうことが重要な課題となります。
[事例]障がいのある方から中途採用のご応募があり、ご本人は就業を希望されたのですがご家族が通勤が不安とのことで反対され実現しなかった。(車通勤で40-50分かかる。冬場の雪、凍結が心配・・・)
ご家族のご心配はよくわかる。ご本人にも大きな負担になる。
障がいのある方にとっては、近くで通勤の負担なく就業できることが望ましい。
その地域に住む人が自らが暮らす地域で就業できる機会をつくることは、その地域で活動する企業の社会的責任でもあると考えます。
すべての企業で障がいのある人を受入れられる社会環境が整うことを願います。
当社で活躍する4人の通勤事情
4人のうち、3人は運転免許を所持しており、自家用車で所用時間6〜8分で通勤が可能。
1人は、バスと徒歩で合わせて1時間以上かけて通勤しているが、バスの運行時刻に無理なく対応できるように、勤務時間を設定しています。
その人が働きやすい制度設計を行なっています。
■ 労働条件・雇用条件
正社員雇用 すべての条件、待遇はまったく同じ
同一労働同一賃金:給与 昇給 賞与 その他手当に差異はない。
作業の切出しはしていない(困難)
他のメンバーと同じ仕事をOJTで日常的に教育訓練し、担当する仕事を増やしている。
できることを増やすことで、他のメンバーとのコミュニケーションも全員が良好。楽しく働くことができている。
学校運営協議会に参加して
2024年4月から、中濃特別支援学校 学校運営協議会委員となり学校運営協議会に参加して、教職員の方々、ご父兄、社会福祉関連のみなさんと懇談させていただく機会を得ました。
卒業生を受け入れる側から、特別支援学校のリアルの一端を学び知ることができ、障がい者を社会が受け入れることの重要性をより一層強く感じています。
また特別支援学校と地域社会との連携の必要性を感じています。
■ 『働きたい!応援団ぎふ』への登録
「働きたい!応援団ぎふサポーター」とは、岐阜県教育委員会が設けている、特別支援学校の生徒たちの就労を支援するための登録制度です。
具体的には、
- 職場見学の受け入れ
- 就業体験(現場実習・企業内作業学習など)の実施
- 校内作業学習における技術指導雇用推進
- 雇用直結型の職場実習の実施や、卒業生の雇用に積極的に取り組む
特別支援学校と企業が一体となって、地域で働き、地域に貢献できる人材を育成することを目的としています。
▶︎ 働きたい!応援団ぎふ サイト
参考になるかも?
中央工機の工場見学をした方が「(この)本と同じですね」と教えてくれました。
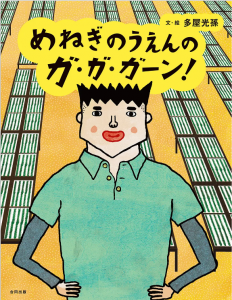
『めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン』
作・絵: 多屋 光孫 出版社: 合同出版
出版社サイト:合同出版 *試し読みができます